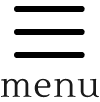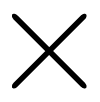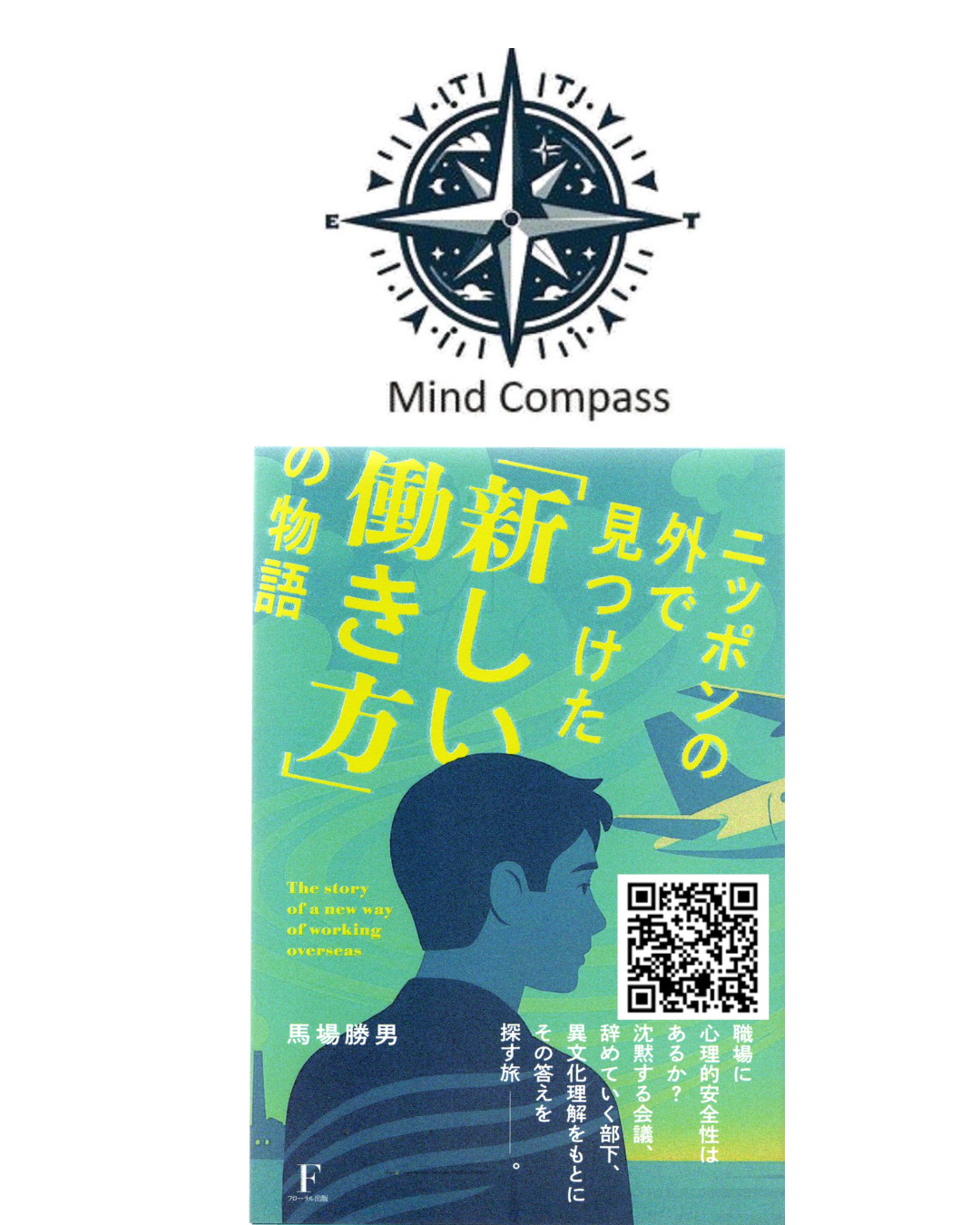AI時代のIQ・EQ・CQ
◆ 弁護士や医師になれるAIの出現と教育の再定義
近年、大規模言語モデル(LLM)の進化により、最新の生成AIが理系・文系の最難関試験である司法試験や医師国家試験に合格可能なレベルに達し、東京大学の入試にも合格水準を超えたという事例が報道されています。(※注1)
私はこの事実に「AIすごい」と驚くよりもむしろ、今の学校教育の大部分、特にIQを中心とした教育内容がAIに代替されうるという点に強い衝撃を覚えています。
実際、教育の主眼はこれまでも技術の進化と共に変化してきました。かつては「読み・書き・そろばん」が基本とされ、読解力・文章作成力・計算力の育成が中心でした。すでに計算は電卓、文章作成はワープロが補完し、漢字を手で書く能力の重要性も相対的に低下しています。
そして現在、AIは自然文の読解や作文までこなします。記憶に関しても、人間が一人で保持できる量には限界がある一方で、AIはインターネット上の膨大な情報を瞬時に活用できます。これらの変化は、暗記を中心とした教育が急速に意味を失いつつあることを示唆しています。
もちろん、すでに教育界でも変革は始まっています。探究学習(※注2)、SEL(社会情動的学習)(※注3)、STEAM教育(※注4)、文理融合的リテラシーといった新たなアプローチが導入されていますが、導入を広げるだけでは不十分であり、学校教育そのものを抜本的に見直す必要があると私は考えています。
◆ AIにできない力:人間のEQとCQを育む教育へ
人間の能力は多面的であり、その捉え方にもさまざまな理論があります。その一つが、IQ・EQ・CQという「3つのQ」による分類です。
- IQ(Intelligence Quotient):論理的思考・言語能力・計算能力などの「認知能力」を示します。主に前頭前野によって担われる領域で、AIが最も得意とする分野です。
- EQ(Emotional Quotient):自己や他者の感情を認識・理解・調整する能力。扁桃体や島皮質など、感情と身体感覚をつなぐ領域が関与しています。
- CQ(Cultural Quotient):異なる文化背景を持つ人々との関係性を築くために必要な、「文化の違いを理解し、適応する能力」です。
特にCQは、まだ一般には耳なじみのない言葉かもしれませんが、グローバル化が進み、国内でも多文化共生が進む中で急速にその必要性が高まっています。
人間の行動や反応は、しばしば文化に根ざした感情によって駆動されます。たとえば、日本では「目上の人に意見を述べることに心理的な抵抗がある」という傾向がありますが、これは高い権力格差志向を背景とする文化的感情反応であり、理屈だけで説明できるものではありません。
このような背景を理解せず、表層的な理由(「常識だから」「世間が許さないから」など)に頼って行動していると、誤解や摩擦が生まれやすくなります。CQやEQの理解がないと、結果として他者との関係に苦しみ、自分でも理由の分からない「生きづらさ」を抱えることになりかねません。
◆ AI時代の教育のチャンス:EQ・CQを学ぶ時間が生まれる
これまでは「知識を詰め込むこと」に多くの時間が費やされてきました。しかし、AIの発展によって、その必要性が薄れつつある今こそ、感情や文化、つまり人間ならではの知性を育む教育へのシフトが可能になってきています。
「覚える」ことから、「感じる」「理解する」「共に生きる」力へ。
EQやCQを育てる教育こそが、AIでは代替できない、人間らしい知性の核であり、それが人間同士の信頼、協力、共感を育みます。そうした力が広がれば、人間関係の摩擦は減り、世界はより平和で幸福なものになると私は信じています。
マインドコンパスの提供するプログラム
〇EQ教育
中四国唯一のEQ6secondsチェンジエージェントとして、SEIサーベイを用いたEQ教育をご提供できます
〇CQ/EQ教育
CWQ認定アソシエイトとしてホフステッドの6次元モデルに準じたCWQサーベイを用いたCQ教育をご提供できます
****
※注1
・司法試験:東大発スタートアップのLegalscape社は、GPT-4を基盤に日本の法律テキストや判例データを組み込んだ法律特化AIを開発し、司法試験短答式で驚異的な成績を収めました。令和6年司法試験(2024年実施)の憲法・民法・刑法(計175点満点)を解かせた比較では、LegalscapeのAIは平均約160点を獲得し、合格基準点93点を大幅に上回る満点水準に達しました。
リーガルスケープのAI、司法試験の選択式全科目でほぼ満点を達成 (2025-05-23) | 株式会社Legalscape | リーガルスケープ
・医師国家試験:東北大学などの研究チームは、日本の医師国家試験2018~2022年の過去問をベースにしたベンチマークデータセット「IgakuQA」を作成し、性能比較を行いました。その結果、GPT-4が全ての年度で合格基準点を超えるスコアを記録し、安定して合格水準に達したことが確認されています。
【論文紹介】モデル評価における「ChatGPTが医師国家試験に合格した」論文から見えた問題点|Cubec(キューベック)
・東京大学入試:2025年の東京大学入試(理科三類を含む全学部)を、最新版のAIに解かせる大規模実験が行われました。これは日本経済新聞・共同通信・河合塾・LifePrompt社の協同企画で、共通テスト+東大二次試験の総合点で合否判定しています。結果、ChatGPT o1モデルとDeepSeek R1モデルの両者が、東京大学理科三類の合格最低点を上回る総合得点を記録しました。
米中のAIが東大入試問題に挑戦。河合塾講師の採点結果が日経新聞はじめ各メディアで報道されました | インフォメーション | 河合塾グループ
※注2
日本では学習指導要領改訂(2020年度~高校で本格導入)により「探究」の授業(総合的な探究の時間)が正式科目化。
※注3
OECDや世界銀行などが近年特に強調しているのが非認知能力(自己効力感、協働性、忍耐力、自己調整能力など)の重要性。PISA(国際学力調査)も、読解・数学・科学だけでなく、2022年から「Creative Thinking(創造的思考力)」を評価対象に追加。日本でも経産省が『未来の教室ビジョン』で非認知能力の可視化や育成を提唱。
※注4
科学(S)・技術(T)・工学(E)・芸術(A)・数学(M)を融合した教育。特に「芸術(Art)」が入っていることが重要で、創造性・感性・ストーリーテリングなど、AIが不得意とする「人間的要素」を学びに取り込もうとしている。